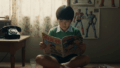1980年代後半(1985年〜1989年)は、日本のマンガ界が「黄金時代」の絶頂期へと到達した5年間です。前章で確立された革新的なラブコメ、ニューウェーブの表現技法、そして青年誌の基盤の上に、巨星『ドラゴンボール』が圧倒的な人気を確立し、『週刊少年ジャンプ』は史上最高部数(約653万部)を記録する**「ジャンプ黄金期」**を現出させました。
しかし、この時期のマンガ史の重要性は、単に一誌の成功に留まりません。他の少年誌や青年誌も独自路線を確立し、表現とジャンルの多様化が一気に進みました。

時代背景:バブル景気と国際的認知の拡大
この5年間は、日本の経済がバブル景気の真っただ中にあり、社会全体が消費とエンターテイメントに対して旺盛な意欲を持っていました。マンガ産業もこの熱狂に乗り、雑誌の発行部数だけでなく、アニメ、ゲーム、キャラクターグッズといった多角的なメディア展開が最高潮に達しました。特に、前章の『AKIRA』の影響もあり、海外での日本のマンガ(MANGA)の認知度が飛躍的に高まり、国際的な文化輸出が本格化しました。
この時代のマンガは、以下の特徴を持っています。
- バトルマンガのインフレとグローバル化: 『ドラゴンボール』がインフレバトルを極致にまで高め、物語のスケールを宇宙規模へと拡大し、世界共通のエンターテイメント言語となりました。
- 青年誌の「専門職」と「社会」描写: 『課長 島耕作』『YAWARA!』といった、ビジネスや特定の専門テーマ、そして大人の日常のリアリティを描く作品が、青年誌の地位を確固たるものにしました。
- アクションとユーモアの都会化: 『シティーハンター』『ジョジョの奇妙な冒険』に代表されるように、アクションの中に都会的な洗練さ、ハードボイルドなユーモア、そして独特のセンスを織り交ぜる手法が成熟しました。
1985年〜1989年:全盛期を築いた7大傑作
この期間は、国民的な人気を誇る作品が多数生まれたため、特に社会現象となり、後世に影響を与えた7作品を厳選します。
| 順位 | 作品名(連載開始/完結年) | 作者名 | 掲載誌 | 時代への貢献と影響 |
| 1 | ドラゴンボール(バトル編本格化) | 鳥山明 | 週刊少年ジャンプ | バトルマンガのグローバル・スタンダードを確立。インフレバトルとスピード感を極致化。 |
| 2 | 課長 島耕作(1983年連載開始) | 弘兼憲史 | モーニング | ビジネスマンガの金字塔。青年誌のサラリーマン読者層を確立し、情報メディアとしての役割を担う。 |
| 3 | シティーハンター(1985年連載開始) | 北条司 | 週刊少年ジャンプ | 都会的なハードボイルドとユーモアを融合。洗練されたアクションと二面性を持つ主人公が魅力。 |
| 4 | 聖闘士星矢(1985年連載開始) | 車田正美 | 週刊少年ジャンプ | ギリシャ神話、星座、美麗な甲冑。後の「美形」バトル路線と女性ファン層開拓の先駆。 |
| 5 | YAWARA!(1986年連載開始) | 浦沢直樹 | ビッグコミックスピリッツ | 柔道を通じ、日常と非日常を丁寧に描写。青年誌のスポーツマンガに新風を吹き込んだ。 |
| 6 | ジョジョの奇妙な冒険(1987年連載開始) | 荒木飛呂彦 | 週刊少年ジャンプ | 独自の世界観、ファッション性、緻密な頭脳戦。後のバトルマンガに異彩を放つ影響を与えた。 |
| 7 | 寄生獣(1988年連載開始) | 岩明均 | アフタヌーン | SFホラーを通じた「生命」の哲学。異形との共存という重厚なテーマで青年誌に深みをもたらした。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
I. 少年誌の圧倒的熱量:『DB』による世界標準の確立
この時代の少年誌、特に『週刊少年ジャンプ』は、『ドラゴンボール』の成功によって、国内外のマンガ界の潮流を決定づけました。
1位:『ドラゴンボール』 — インフレバトルの完成形と世界席巻
前章でその才能を開花させた鳥山明氏の『ドラゴンボール』は、この5年間で物語を「サイヤ人編」「フリーザ編」といった、世界を股にかけた壮大なバトルへと移行させました。
【強さのインフレーション】 『ドラゴンボール』の最大の功績は、「戦闘力」という数値や「超サイヤ人」という変身を導入し、敵の強大さに合わせて主人公が限界を超えて強くなるという「インフレバトル」の構造を確立した点です。これにより、物語のスピード感と予測不能性が最大化され、読者は毎週の展開に熱狂しました。この手法は、後の少年バトルマンガの基本的なテンプレートとなりました。
【鳥山デザインのグローバル性】 そのキャラクターデザインとアクション描写は、国境を越えて熱狂的に受け入れられ、アニメ、ゲーム、グッズといったメディアミックス戦略も最高潮に達しました。日本のアニメ・マンガ文化を世界に輸出した「MANGA」の顔として、その後の文化交流に計り知れない影響を与え続けました。
4位:『聖闘士星矢』 — 神話の世界観と美形バトルの先駆
車田正美氏の『聖闘士星矢』は、従来の熱血バトルに、**ギリシャ神話、星座、そして美麗な甲冑(クロス)**というファンタジー要素を融合させたことで、新しいファン層を開拓しました。
【美形キャラクターの集団】 主人公たち「青銅聖闘士」だけでなく、敵である「黄金聖闘士」も含め、美形キャラクターが多く登場したことで、特に女性読者を大量に取り込むことに成功しました。聖闘士たちの**「宿命」や「悲劇」**を描くドラマチックな展開は、キャラクターへの感情移入を深めました。
【設定の緻密化の重要性】 「小宇宙(コスモ)」という精神エネルギーの概念、複雑な階級制度、そして星座に連動した聖衣のデザインなど、緻密な設定が世界観の深みを増し、後のファンタジーバトルマンガにおける「設定重視」の流れを加速させました。
6位:『ジョジョの奇妙な冒険』 — 独自センスと頭脳戦の胎動
荒木飛呂彦氏の『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年の連載開始当初はハードな吸血鬼バトルでしたが、すぐに**「スタンド」**という独自の能力概念を導入し、少年マンガ界に異彩を放ち始めました。
【唯一無二のセンス】 荒木氏独自の、ファッション性の高いキャラクターデザイン、強烈な擬音表現、そして哲学的なセリフ回しは、他の追随を許さない世界観を作り上げました。特に、この作品で確立された「スタンド」は、単なる力の強さだけでなく、**能力の特性を活かした「頭脳戦」や「トリック」**を重視するものであり、後のマンガにおける「知的バトル」の方向性を決定づける重要な胎動となりました。
II. 青年誌の成熟:大人のリアルと専門性
前章で基盤が築かれた青年誌は、この5年間で社会人や大人の読者をさらに深く取り込み、情報メディアとしての役割も担うようになりました。
2位:『課長 島耕作』 — サラリーマンの代弁者と出世物語
弘兼憲史氏の『課長 島耕作』は、この時期にまさに「サラリーマンのバイブル」として国民的な人気を獲得しました。
【ビジネスマンガの確立】 大企業「初芝電器産業」を舞台に、主人公・島耕作の出世と、その過程で出会う複雑な人間関係、社内の派閥争い、そして大人の恋愛を描きました。この作品のヒットは、マンガが**「ビジネス情報」「社会の構造」**を扱うメディアとしても有効であることを証明し、「ビジネスマンガ」というジャンルを確立しました。
【バブル期の社会描写】 当時のバブル景気の熱狂と、その裏にある企業戦士たちの孤独や葛藤を克明に描写し、現役のサラリーマンたちから絶大な共感を呼びました。この作品の成功により、青年誌は学生だけでなく、社会人にとっても「必読」のコンテンツとしての地位を確立しました。
5位:『YAWARA!』 — スポーツを通じた女性の自立と日常
浦沢直樹氏の『YAWARA!』は、柔道というスポーツを題材にしながらも、その本質は**「普通の女の子の幸せ」**を求める主人公・猪熊柔の等身大の青春と成長を描いた作品です。
【日常と非日常のバランス】 柔道という非日常的な才能と、普通の恋愛や学生生活を送りたいという日常的な願いとの葛藤を丁寧に描くことで、読者は柔の人間的な魅力に強く共感しました。従来のスポーツマンガのような熱血一辺倒ではなく、キャラクターの心理と日常のリアリティに焦点を当てた手法は、特に女性読者からの支持を広げ、青年誌の読者層の多様化に貢献しました。
7位:『寄生獣』 — 生命の哲学とSFホラーの深化
岩明均氏の『寄生獣』は、『アフタヌーン』で連載されたSFホラーの傑作であり、この時期の青年誌が持つ**「哲学的な深み」**を象徴する作品です。
【人間と他の生命の共存】 地球上に突如現れた寄生生物と、右手を乗っ取られた主人公・泉新一の物語です。この作品は、人間が他の生命に対して持つ傲慢さや、生存本能という根源的なテーマを深く掘り下げました。そのメッセージ性の高さは、単なるホラーやアクションの枠を超え、読者に**「生命とは何か」「正義とは何か」**という哲学的な問いを投げかけました。
III. 1985年〜1989年 総括:全盛期の確立と次世代への移行

この5年間は、日本のマンガ界の持つエネルギーが最高潮に達し、後の時代へと続く重要な潮流が生まれた時期です。
【王道の確立と進化】 『ドラゴンボール』によってバトルマンガの世界標準が確立され、『聖闘士星矢』によってその表現がファンタジーの方向へと多様化しました。少年誌は、強大な力、壮大な冒険、そして不屈の友情という、普遍的なテーマを極致にまで高めました。
【青年誌の社会浸透】 『島耕作』の成功により、マンガはもはや学生の娯楽ではなく、社会人にとっても仕事のヒントや教養、そして共感を得るための重要な情報メディアとしての地位を確立しました。青年誌は、多角的なテーマを取り込むことで、読者層と発行部数を確実に増やしました。
【表現技法の成熟】 『シティーハンター』の洗練された都会派アクションや、『ジョジョの奇妙な冒険』の持つユニークな世界観と知的バトル要素は、マンガ表現の多様性が成熟したことを示しています。この時期に確立された「熱量」と「多様性」こそが、続く1990年代