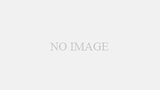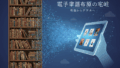2020年〜2024年の5年間は、日本のマンガ界が**「コロナ禍によるライフスタイルの激変」と「グローバル・デジタル時代の本格化」**を背景に、表現、流通、そして消費形態のすべてにおいて構造的な変革を遂げた時代です。従来の枠組みを打ち破るウェブコミックの台頭と、アニメを中心とした世界的なメディアミックス戦略が完成し、市場は史上最高を更新し続けました。
この時期、マンガは従来の「雑誌で読むもの」から**「スマートフォンで楽しむ総合カルチャー」**へと完全に進化しました。
時代背景:巣ごもり需要、ウェブトゥーン、AIの萌芽
この時期のマンガ界は、以下の社会的・技術的変化から大きな影響を受けました。
- 巣ごもり需要と電子市場の爆発的成長: コロナ禍による外出自粛が、人々のエンタメ消費をデジタルへと集約させ、電子書籍の販売が爆発的に増加しました。マンガ単行本の販売額は、電子コミックが紙を上回り、市場の主役は完全にデジタルへと移行しました。
- ウェブトゥーンの日本市場参入: 韓国発の「ウェブトゥーン(縦読み・フルカラー)」が日本の資本と融合し、専用プラットフォーム(ピッコマ、LINEマンガなど)を通じて本格的に市場に参入しました。「スキマ時間」に最適化されたこのフォーマットは、特に若年層やライトユーザーに定着し、マンガの表現方法とビジネスモデルに新たな選択肢を提示しました。
- メディアミックスのグローバル戦略完成: VODサービスを通じたアニメの国際同時配信が常態化し、新作のヒットは連載初期から「世界同時ブーム」となることが前提となりました。制作側は最初からグローバルな視点と、アニメ化に適したストーリー構造を意識するようになりました。
- AI技術の萌芽: 作画アシスタントとしてのAIツールが普及し始め、マンガ制作の現場にもデジタル技術がより深く浸透し、制作スピードとクオリティの向上が図られました。

この時代のマンガは、以下の3大特徴を持っています。
- メディアミックスの常態化とデジタル・グローバル化: 連載開始とほぼ同時にアニメ化・世界配信を前提とした戦略が主流となり、デジタル配信と連動して世界的に同時展開されました。
- ジャンルの大胆な融合とニッチのメジャー化: 従来の枠にとらわれず、複数の要素を組み合わせたハイブリッドな作品が新しい読者を獲得し、特にウェブコミックでこの傾向が顕著になりました。
- 「大人向け」の再評価と物語の普遍性(成熟の時代): 社会的な閉塞感を背景に、内省的・哲学的なテーマを持つ作品が評価され、読者の成熟に応える普遍的なメッセージが求められました。
2020年〜2024年:デジタル変革とジャンル融合の極致を象徴する7大傑作
| 順位 | 作品名(連載開始/完結年) | 作者名 | 掲載誌/媒体 | 時代への貢献と影響 |
| 1 | 呪術廻戦(2018年連載開始) | 芥見下々 | 週刊少年ジャンプ | 現代ダークバトルの世界的ブームを牽引。アニメとの強力な相乗効果で巨大市場を形成。 |
| 2 | SPY×FAMILY(2019年連載開始) | 遠藤達哉 | 少年ジャンプ+ | ウェブコミックの代表作の一つ。スパイ×ホームコメディという融合ジャンルで老若男女に人気。 |
| 3 | 【推しの子】(2020年連載開始) | 赤坂アカ/横槍メンゴ | 週刊ヤングジャンプ | 芸能界の闇をテーマに、サスペンスとアイドルを融合させた、批評性の高いヒット。 |
| 4 | 葬送のフリーレン(2020年連載開始) | 山田鐘人/アベツカサ | 週刊少年サンデー | **「冒険後の物語」**という静かなテーマで大ヒット。読者の成熟に応える普遍的なメッセージ性。 |
| 5 | チェンソーマン(2018年連載開始) | 藤本タツキ | 週刊少年ジャンプ/少年ジャンプ+ | 過激な表現と芸術性。インターネット世代のニヒリズムとカオスを体現。 |
| 6 | ダンダダン(2021年連載開始) | 龍幸伸 | 少年ジャンプ+ | オカルト×バトル×ラブコメの融合と、デジタル時代の高度な作画技術を体現。 |
| 7 | 怪獣8号(2020年連載開始) | 松本直也 | 少年ジャンプ+ | ウェブコミックから生まれた異色の王道。大人になった主人公による再起の物語。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
I. デジタル・プラットフォームの覇権と新たな才能
この時代は、集英社の「少年ジャンプ+」に代表されるウェブコミックプラットフォームが、従来の週刊誌と並ぶ、あるいはそれ以上の影響力を持つに至り、才能発掘の主要な場所となりました。
2位:『SPY×FAMILY』 — ウェブコミックの大看板
遠藤達哉氏の『SPY×FAMILY』は、ウェブ連載専門誌である**『少年ジャンプ+』の看板作品**として、紙媒体発の作品と肩を並べる、あるいは凌駕する人気を獲得しました。
【ウェブ連載の成功モデル】 ウェブ連載は、週刊誌の制約にとらわれず、読者の反応を見ながら、単行本にまとめた際に最も魅力的な構成を追求できます。本作は、その柔軟性を活かし、「スパイアクション」の緊迫感と「ホームコメディ」の癒やしという、従来なら両立が難しかったジャンルを巧みに融合させました。この成功は、ウェブ発マンガがニッチではなく、老若男女に愛されるメジャーコンテンツになり得ることを証明しました。
6位:『ダンダダン』 — 作画技術とネット文化の融合
龍幸伸氏の『ダンダダン』も『少年ジャンプ+』発の作品であり、オカルト、バトル、ラブコメという複数の要素を過剰なまでに盛り込んだ、ハイブリッドなエンターテイメントとして評価されました。
【デジタル作画の極致】 龍氏のダイナミックで緻密な作画は、デジタル制作のメリットを最大限に活かしており、特にアクションシーンの迫力は紙面を超える勢いがあります。また、作品全体に漂う、インターネットのミームやオカルト都市伝説といった現代的な要素が、デジタルネイティブ世代の読者に強く共感されました。この作品は、ウェブ連載という自由な媒体だからこそ実現した、スピード感と密度の高い表現の極致と言えます。
7位:『怪獣8号』 — ウェブが生んだ「大人の王道」
松本直也氏の『怪獣8号』も『少年ジャンプ+』発で、**「大人になった主人公の再起」**という、少年誌の枠を超えたテーマを描きました。
【普遍的な「夢の再挑戦」】 怪獣と防衛隊という王道的な設定を用いながらも、夢を諦めきれない32歳の主人公が再び夢に挑戦するというストーリーは、ウェブコミックの読者層の広がり、特に「大人」の読者の共感を深く集めました。ウェブで連載されながらも、その物語構造は極めて王道であり、デジタルが新たな「王道」の供給源となったことを示しています。
II. メディアミックスの完成と世界市場の掌握
この時期のメガヒット作品は、アニメのクオリティとVODによる世界同時展開がセットとなり、グローバルな文化現象を生み出しました。
1位:『呪術廻戦』 — 世界同時ブームの確立
芥見下々氏の『呪術廻戦』は、『鬼滅の刃』後の少年誌を牽引し、**「メディアミックスによる世界同時ブーム」**という構造を確立しました。
【現代社会の不安とダークヒーロー】 現代社会に潜む「呪い」と戦う呪術師たちの物語は、そのダークな世界観、スタイリッシュなアクション、そして主要キャラクターの死も厭わない緊張感ある展開が、現代の読者に深く刺さりました。アニメ化によって、そのバトルシーンの迫力と複雑な世界観が世界中のVODサービスを通じて瞬時に共有され、原作単行本の売上を世界規模で爆発させました。
5位:『チェンソーマン』 — 芸術性とカオスの具現化
藤本タツキ氏の『チェンソーマン』は、週刊誌からウェブへとプラットフォームを移しつつ、極めて前衛的な表現と物語構造でカルト的な人気からメジャーへと躍り出ました。
【インターネット世代のニヒリズム】 従来の常識や倫理観から逸脱した、暴力、ユーモア、そしてニヒリズムが混在する作風は、**インターネット時代特有の「カオス」や「虚無感」を体現していると評価されました。アニメ化に際しても、原作の芸術的な側面を尊重した制作がなされ、単なるバトル作品としてではなく、「現代の芸術作品」**として国内外の若いクリエイターやファンに多大な影響を与えました。
III. ジャンルの破壊と「成熟」した読者への問いかけ
この時代は、従来のジャンルの常識を破った作品や、読者の成熟度に応える深いテーマの作品がメジャーな地位を占めました。

3位:『【推しの子】』 — 批評性を持ったジャンル融合
赤坂アカ氏(原作)、横槍メンゴ氏(作画)による『【推しの子】』は、**「アイドル」というエンタメの最前線を舞台に、「サスペンス」と「転生」**という異色の要素を融合させました。
【芸能界の闇と現代社会の批評】 単なる芸能界の華やかさを描くのではなく、スキャンダル、SNS、炎上、そして業界の構造的な闇といった現代社会の批評性を強く持ちました。この作品の成功は、デジタル時代において、読者がエンタメの「裏側」や「真実」に対して強い関心を持っていることを示しており、マンガがゴシップや社会問題に切り込むメディアとしての役割を強めたことを象徴しています。
4位:『葬送のフリーレン』 — 冒険後の静謐な哲学
山田鐘人氏(原作)、アベツカサ氏(作画)の『葬送のフリーレン』は、**「冒険後の世界」**という極めて異質なテーマで、マンガ界に静かなブームを巻き起こしました。
【普遍的なメッセージと内省】 勇者たちによる魔王討伐後の世界を舞台に、千年を生きるエルフの魔法使いが、人間の仲間たちの死を通じて「感情」や「時間の重み」を理解していく物語です。熱血なバトルや派手な展開よりも、登場人物たちの**繊細な心情、後悔、そして普遍的な「生きる意味」**を描くことで、特に大人の読者から深く支持されました。この作品の成功は、読者が内省的で哲学的なテーマを求めるほどに、マンガという媒体が成熟したことを示しています。
IV. 2020年〜2024年 総括:マンガ・カルチャーの完成形
2020年代前半は、日本のマンガが**「デジタル・グローバル・ハイブリッド」**という、現代のコンテンツ産業の完成形に到達した時期です。
【プラットフォームの多様化と競争】 ウェブコミックプラットフォームが、従来の週刊誌に匹敵する、あるいは凌駕する作品を次々と生み出し、クリエイターの活躍の場が劇的に広がりました。ウェブトゥーンの参入は、マンガのフォーマット自体にも変化をもたらし、デジタル表現の多様化を促しました。
【世界市場の掌握】 『呪術廻戦』『SPY×FAMILY』などのメガヒットが、アニメとの強力な連携により世界中のファンに受け入れられ、日本のマンガ産業は世界的な文化輸出の柱としての地位を確固たるものにしました。
【テーマと表現の自由】 ジャンルの壁はほぼ消滅し、『【推しの子】』のような社会批評性の高い作品や、『葬送のフリーレン』のような哲学的な作品がメインストリームで成功しました。これは、読者の成熟と、マンガ家の表現の自由度が極限まで高まったことを示しており、マンガというカルチャーが現代社会のあらゆるニーズに応える、最も柔軟で強力な芸術表現として進化し続けている証左です。